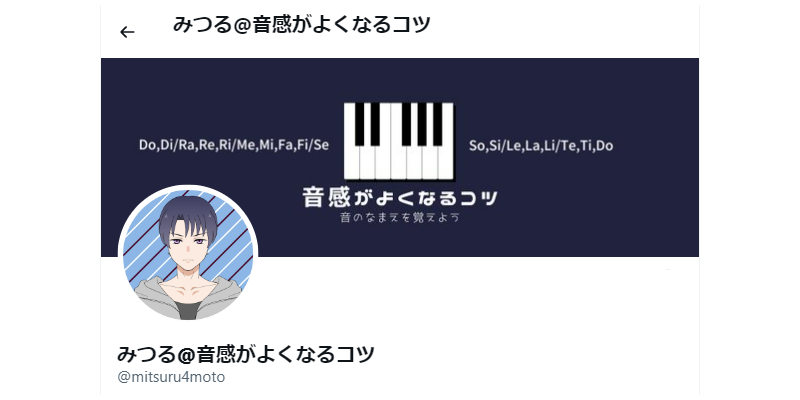この記事で身につくこと
- ビアノ88鍵の音の呼び方(音名おんめい)
- メロディを歌うときの音の呼び方(階名かいめい)
- 音名と階名の役割
なぜ呼びかたを覚えるのか
安心してください。このブログで僕が「覚えてください」とお願いするのはたぶんこの記事だけ。音の名前を覚えるのは「その音を聞き取れるようにする」ためです。
人間は名前を知らないものは呼べない=覚えられません。人間にはどう呼んでいいかわからないものは認識できないという性質があるからです。
「音がわからない」というかたは多いと思いますが、音楽に興味がなくてなんと呼ぶか知らないひとがほとんどだと思います。
逆に名前を覚えて何度も呼んでいるとどんどん距離が縮まってなかよしに。人との付き合いと同じ。好きな音となかよくなりましょう。
音名(おんめい)と階名(かいめい)
まず画像をどうぞ。ピアノの中央右側の図です。

上段
CDEFGABが音名(おんめい)
下段
Do Re Mi Fa So La Ti が階名(かいめい)
これまで普通に慣れ親しんだ日本語のドレミファソラシドは使いません。正確には使えません。理由はのちほど説明します。
同じ音にたいして、いつも音名・階名の二通りの呼び名があることを知っておいてください。
音名
音名について見ていきます。ピアノの88鍵盤をイメージしてください。
鍵盤ひとつひとつに音名がついていてこれはいつでも同じ。
変化することなくピンポイントで音(の高さ)をあらわします。
音名の数字は音の高低を表します。数字はCで切り替わります。
ピアノの鍵盤はいちばん左の低いところから、
A0 A#0/Bb0 B0
C1 C#1/Db1 D1 D#1/Eb1 E1 F1 F#1/Gb1 G1 G#1/Ab1 A1 A#1/Bb1 B1
C2 C#2/Db2 D2 D#2/Eb2 E2 F2 F#2/Gb2 G2 G#2/Ab2 A2 A#2/Bb2 B2
C3 C#3/Db3 D3 D#3/Eb3 E3 F3 F#3/Gb3 G3 G#3/Ab3 A3 A#3/Bb3 B3
C4 C#4/Db4 D4 D#4/Eb4 E4 F4 F#4/Gb4 G4 G#4/Ab4 A4 A#4/Bb4 B4
C5 C#5/Db5 D5 D#5/Eb5 E5 F5 F#5/Gb5 G5 G#5/Ab5 A5 A#5/Bb5 B5
C6 C#6/Db6 D6 D#6/Eb6 E6 F6 F#6/Gb6 G6 G#6/Ab6 A6 A#6/Bb6 B6
C7 C#7/Db7 D7 D#7/Eb7 E7 F7 F#7/Gb7 G7 G#7/Ab7 A7 A#7/Bb7 B7
C8
88全部書きました。
#(シャープ) 半音(鍵盤ひとつ)上がる
b(フラット) 半音(鍵盤ひとつ)下がる です
ピアノの鍵盤を見れば音名はわかります。とくに覚える必要はありません。
階名
Do Re Mi Fa So La Ti です。
ここではいままでシだと思っていた音はTi(ティ)だということだけ覚えてください。レは喉奥から出てくるRの音なので「ウェ」のように聞こえます。発音は実際の音で確認してください。
イメージがつかみにくいと思うので動画をどうぞ。
見ていただくとDo Re Miが繰り返すたびに音が高くなっていくことに気付かれたと思います。階名はひとつながりの音の流れを表していて、それは相対的な関係なので、Doはどの高さからはじまってもよいことがわかります。
階名の半音(#シャープ)
階名の場合
#(シャープ) 半音(鍵盤ひとつ)上がる は子音がiにかわります。
例外はありません。

So が Si(シ)に変化しています。
これが音のかぶるカタカナのドレミが使えない理由です。
Wikiなどをみていただくとわかるのですが、実は階名についてはこれまで異常なほどたくさんのパターンが各国で試みられてきています。
それぞれ利点はあったのかもしれませんが、要するに我々が慣れ親しんできたカタカナのドレミもローカルルールの一つに過ぎないということです。
もう21世紀ですからこれから覚えるならユニバーサルなルールの方がよくないですか?
「半音上は子音i」は分かりやすいルールですから、SiはSoの#と覚えてしまいましょう。
曲の中でもよく出てくる音です。
余談ですが、Mi と Tiは半音上がFa と Do です。
間の音がないので子音がiに変化する必要はありません。
半音上を子音iにするのは理にかなっています。
階名の半音(bフラット)
b(フラット) 半音(鍵盤ひとつ)下がる は子音がeにかわります。
例外はひとつだけあります。
Reはすでに子音にeを使っているので半音下がるとRaになります。

おつかれさまでした。以上で
①ピアノの88キーの音名A0~C8が言える
②黒鍵を含めたDo Re Mi 12音17種類が言える ようになっています。
つまり 音の名前を《すべて》知っています。 音の名前について覚えることは 以上で終わり。この他にはなにもありません