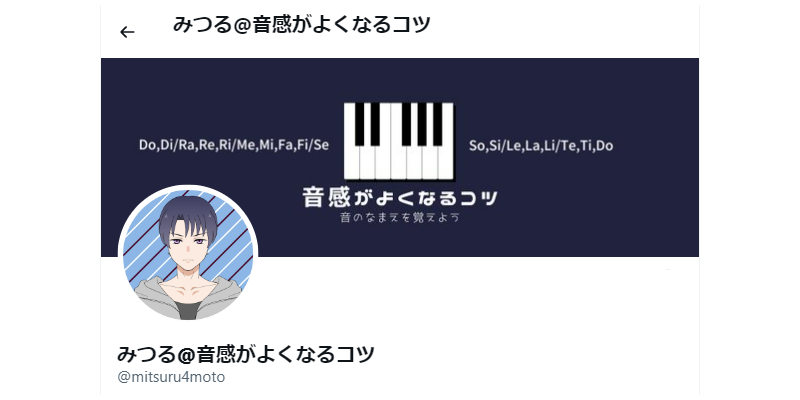さんざんわかりにくいと文句をつけてきた、伝統的なコード表記ですがそのメリットがわかりました。とあるレクチャー動画を見たからなんですが、なるほど!と合点がいきました。どういう場面でそれが生きるのか。この記事ではアルファベット(と記号)を使った伝統的なコード表記およびその考え方が活用できるシチュエーションとその理由について、考えてみたいと思います。そしてポピュラーソングを右手でメロディ、左手でコードをおさえてひく場合になぜ「有効でなくなるのか?」をあらためてご説明したいと思います。

この記事でわかること
- アルファベットコード表記のメリット
- コードネームだとわかりにくいシチュエーション
- なにが明確なほうがいいか?
音楽におけるキャッチーな要素とは?
それはいうまでもなく「繰り返し」です。先が予想ができることでぼくたちの印象に残ります。キャッチーな音楽がどのようなものかについてはこちらの記事をごらんください。
「同じ」と認識されるのは?
一般的にはメロディのくりかえしですが、インターバル(音の高さの間隔)が同じ音のかたまりも、また同じものと認識されます。のちほど紹介させていただく動画にでてくるのですが、つぎのようなパターンは耳に心地よく感じることがあります。

また、こんなパターンもあります。今度はマイナー。アンビエントな曲に出てきそうです。

くりかえしはなぜ心地いいのか?
予測したものがその通りになるから、だと考えられます。最初のいくつかを聞いた段階で、ひとはパターンをとらえている可能性があります。それに基づいて次も無意識に予測しているので、同じパターンの音の連なりはその予想を現実化することで、わたしたちに心地よさを与えます。この予測のもたらす心地よさについては、こちらの記事にまとめました。
コード表記のメリット
以上からわかるコード表記のメリットはなんでしょうか?それは、機械的に繰り返されるフレーズは一発でわかるということ。ルートを基準に「同じこと」がおこなわれるのであれば、自分が何をしているか?を理解する必要はありません。同じように指を持っていけば演奏が可能です。プレイヤーとしてはこれは心強いはず。おなじことをするなら、コードの形が同じ。そのコード「フォーム」をおぼえてしまえば、おさえる場所がわかります。
典型的なのはアルペジオモード
シンセにはアプリでもハードでもアルペジエーターがついていることが多いですが、あれがならしてくれるのがこのスタートをかえても同じパターンですね。実用になるのはそれが繰り返しによってキャッチーなフレーズになるからだと思われます。つまり時と場合によっては非常に強力な武器になります。
ポップスでいまひとつ使えない理由は
同じフォームで押し通す技がポップスで使えないのは、メロディが歌っているから。歌が最優先なので、アルペジエーター的なゴリ押しはではできません。歌ものでは音階にそったダイアトニックコードをベースに伴奏が構築されます。上記の譜例でもkey=Cの音階外の音が登場していますが、こうした音はメロディと衝突してしまいます。メロディは耳慣れたものになるよう音階内の音を基準に作られているからです。
ポップスの伴奏としてのコード
ポップスの伴奏としてのコードは大部分がダイアトニックコード。変化したものは例外なので、逆に変化していることがハッキリわかったほうがいい。たとえばⅢm7のコードstrMは普段はMとあらわしてしまって全く問題ありません。一例ですがセカンダリードミナントに変化したときsitrMと書いておけばいいという考えかたができます。すると演奏するほうも、どこに注意したらいいか見通しが良くなると思います。これがダイアトニックなのか違うのか、いちいち判断していくというのはムダではないでしょうか? コードネームで書いている限りは表記のしかたはどんなコードネームでも一緒。ぼくは初心者にはやさしくない点と考えます。
階名で表現すると
フォームが同じということが一目でわかりにくくなる。それはその通り。しかし、その場合は併記すれば全く問題ないと思います。そうしたことが求められるケースは限定的なのはすでに検討したとおりですし、レアケースのために日常的にガマンを続けることには積極的な意味はないのではないでしょうか?注意すべきところを目立たせる。習得にはたぶんその方が利点が多い。音階外の音は2文字になるコードの階名表記は、とりあえずそれが現状でも実現できているのではないか?と考えています。
参考になった動画
こちらの動画になります。美しい音の構築の基本的なアイディアが学べました。
いかがだったでしょうか?
チャンネルのコンテンツとして、ポップスをピアノでカンタンにひく動画を整備するのは今後の目標。見せ方も含めていろいろ考えなければならないことがありますが、そのための準備を進めていきたいですね。それではまた次回のブログでお目にかかりましょう。