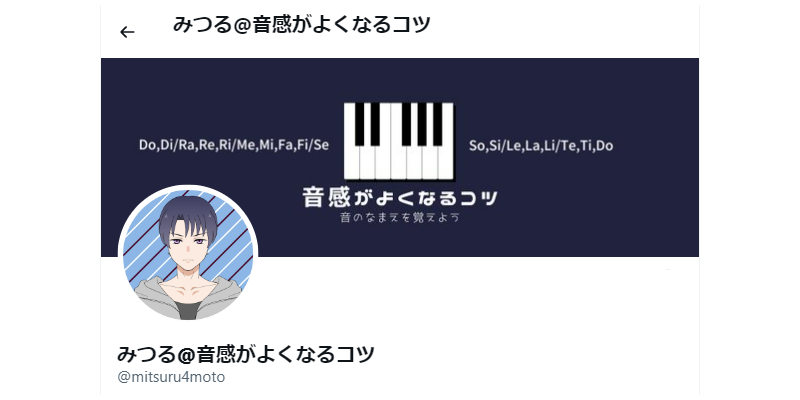いよいよピックをもって機械的なギターの練習をはじめました。しかし、どうもしっくりきません。とくにクロマチック練習。やっていて「わけがわからなくなる」というのがその原因です。とはいえ、指はスムースに動くにこしたことはありません。そこで一番おぼえやすいポジションをさがしました。おすすめは78910の4フレットを使うことです。
この記事ではその理由を説明します。大きく2つがありますので、これからクロマチック練習を始める人の参考になればと思います。当分のあいだは僕もこれだけを練習します。
恐怖!機械的に指を動かすとどうなる?
まず気を付けて欲しいことは、練習がかえって音感を悪くするかも?ということです。
Geminiに聞いてみました。
「音と結びつかない指の練習は混乱をまねき、かえって音感を悪くする」という考えは、全面的に正しいと言えます。それは、多くの熟練したミュージシャンが共有する、練習における核心的な哲学です
機械的に指を動かすだけの練習は、例えるなら「キーボードの配列を覚えるために、意味のない文字列をひたすら速く打つ」ようなものです。確かにタイピング速度は上がるかもしれませんが、文章を作成する能力や語彙力は全く向上しません。
ギターも同様で、指が速く動くようになっても、どの動きがどの音に対応するのかを脳と耳が理解していなければ、音楽的な演奏には繋がりません。
なぜ「音と結びつかない練習」が危険なのか
「混乱」や「音感の悪化」は、具体的に次のような形で現れます。
運動と聴覚の分離
人間の脳は、特定の動き(運指)と、それによって生まれる結果(音)をセットで記憶します(これを運動記憶と聴覚的フィードバックの連携と呼びます)。音を意識しない練習は、この連携を無視するため、「指は動くけれど、自分が何の音を出しているかわからない」という危険な状態に陥ります。
間違った音への無自覚
音を意識していないため、練習中に間違った音(ミストーン)を出しても、それを「間違い」として認識できません。むしろ、その間違った運指と音の組み合わせを脳が記憶してしまい、間違った音感が定着するという最悪の結果を招きかねません。
音楽的表現への応用ができない
いざメロディーやソロを弾こうとした時、頭の中に鳴っている「この音を出したい」というイメージと、指の動きが結びつきません。結果として、速いだけで音楽的ではない、無機質な演奏になりがちです。
正しいクロマチック練習は音を理解しながら
機械的な練習の弊害については以上の通り、すると、「音を理解しながら」クロマチック練習ができるポジションを選ぶべきだということがわかります。
シャープやフラットがなるべくついていないところを選ぶとよさそうですね。

1-4 フレット: 12個
2-5 フレット: 15個
3-6 フレット: 13個
4-7 フレット: 15個
5-8 フレット: 16個
6-9 フレット: 13個
7-10 フレット: 17個 👑
8-11 フレット: 13個
9-12 フレット: 14個
10-13 フレット: 15個
11-14 フレット: 13個
12-15 フレット: 17個 👑
という訳で、7-10は真っ先に候補になります。24音のなかで、ハズレは7音しかないからです。あとは全部音階CDEFGAB(drmfslt)の音におさまります。

確認してみると、音階のCDEFGABに飛びや抜けもありません。完璧です。
以上が7フレットから始める理由の1
もう一つの理由その2はフレット位置がネックの中間くらいで、フレットの幅も広すぎず狭すぎず弾きやすいからです。

音の呼び方
はじめてのひとにはちょっと注釈が必要になりますが、半音にも呼び名があって、音の呼び方はきまっています。12音は大体の場合以下のようにあらわします。
C,Db,D,Eb,E,F,F#,G,Ab,A,Bb,B
よびかたは、
Do,Ra,Re,Me,Mi,Fa,Fi,So,Le,La,Te,Ti
になります。
Le,Laはそのまま日本語で「レ」「ラ」でOKですが、
Ra,Reは「ワ(ウヮ)」「ウェ」みたいな感じになります。
僕もいまだに完全に身についているとは言えませんが、まあ、郷に入れば郷にしたがえなので、ゆっくりやって行けばいいと思います。音の読み方についてはこちらの記事も参照してみて下さい。
で、僕の場合は一応半音も含めて認識は出来るようになっているので、ゆっくり音の名前を歌いながら、クロマチック練習をやって行くことになります。
音が認識できないというひとは、無理をする必要はないと思います、クロマチック練習はまだ必要ないし、上に書いたような理由でむしろやらない方がいいのではないでしょうか?
ギターで音階を覚える方法と、半音を身につける方法については、以下の記事を参考にしてみて下さい。
おつかれさまでした
以上ザックリ目を通していただければ、ギター上での半音のとらえ方がわかると思います。クロマチック練習はまずは音階が弾けるようになって、音を把握できるようになり、さらに半音もわかるようになった、その後でもOKという感じじゃないか?と思います。それまではスケール練習で十分なのではないでしょうか?
それにしても記事を書いている自分すら関連記事が探すのがたいへんというのが、このブログの問題点ですね()。気づいた都度その場で記録しているもので、すみません。そのうち分かりやすく整理したいと思います。それではまた次回のブログでお目にかかりましょう!