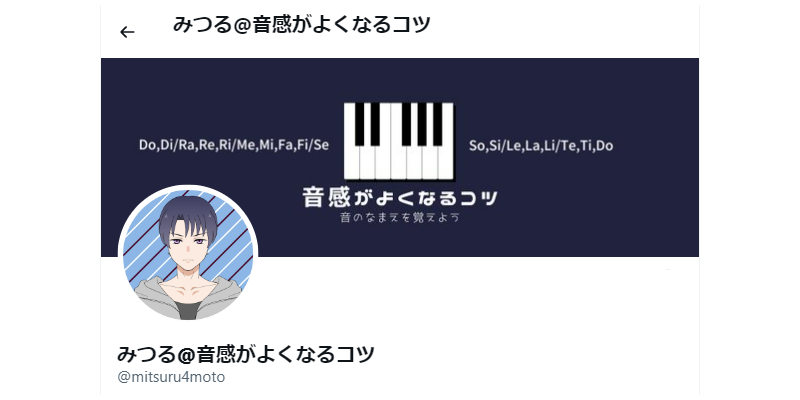音源を解析してキーとコードを教えてくれる便利なWebサービスのChordifyやMoises。音楽をまなぶのに楽しく使わせてもらっていますがコード表示は当然クラシックスタイルw。そこで今回はみつる式のコード表記にしたらどうなるのか?簡単な早見表をつくってみました。Webサービスを利用されていないかたにも役に立つ早見表になっていますのでどうぞお役立てください。
この記事でわかること
- Webサービスのコード解析
- シンプルな対応表
- コードの基本的な押さえ方
こんな表になっています


Webサービスのコード解析
基本的に判別はキーとトライアドのコードまでですね。ハーモニーに関してはメロディをどこまでこまかく拾うかという話になってしまうのでこれはこれで見識かな?というふうに僕はとらえています。そこで先ほどの表ですがWebに表示されるのはこうしたコードネームになります。同時に曲のkeyも必ず表示されているはずなので使い方としては、
1)keyを確認
2)そのkeyの列を見る
3)どのコードが表示されているか見る
4)表の一番ひだりでみつる式のひきかたを確認する
5)コードをおさえる
以上の手順になります。階名表示だと12のキーのどれでもコードは一つの表記で示すことができます。キーが違っても曲の中での「役割」は同じというわけですね。
コードのおさえかた
具体的なコードのおさえかたについてはこちらの記事をご参照ください。鍵盤図付きで全12key解説しています。
《永久保存版》みつる式超かんたんコードネームでおぼえるダイアトニックコード12key完全攻略レシピ
解説だけだと味気ないので曲としてひいてみてください。
YAMAHA PSS-A50完全対応「ダイアトニックコード全key分覚えられるソング」こんどこそ全曲分です!
それではまた次のブログでお目にかかりましょう!
今日のGPT
みつる:音楽のコードネームが難しくておぼえられません。ピアノでかんたんにひけるようになるコツはありませんか?
ChatGPT:音楽のコードネームを覚えるためには、以下のコツが役立つかもしれません。
- 頻繁に演奏してみる 最も簡単な方法は、定期的にピアノでコードを演奏することです。慣れるまで同じコードを何度も演奏し、そのコードの響きや形状を覚えるようにしましょう。
- コードチャートを使う コードチャートとは、指の配置やコード名を示したグラフィックスです。チャートを見ながら、各コードの名前と形状を覚えることができます。
- 似たコードをグループ化する 似た形状を持つコードをグループ化することで、覚えやすくなります。例えば、C、F、Gなどは “主要三和音” と呼ばれるグループに属するため、一度に覚えることができます。
- コード進行を演奏してみる コード進行を演奏することで、実際に曲を演奏しているような感覚を得ることができます。最初は簡単なコード進行から始め、徐々に難易度を上げていきましょう。
- 音楽理論を学ぶ コードの構造や関係性を理解することで、コードネームを理解しやすくなる場合があります。音楽理論の基礎を学び、和声の理論やコードの種類などを理解することができます。
以上の方法を使って練習し、コードネームを覚えていくと、徐々にピアノでかんたんに演奏できるようになるでしょう。